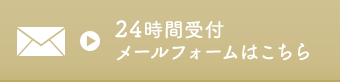こんにちは、杉並区浜田山のなんば鍼灸院・整骨院、院長の南波です。
数あるブログの中から、本ブログを読んで頂き感謝致します!
今回は「塩」についてお伝えしたいと思います。
塩はどれも同じではない
私たちの身体にとって欠かせない「塩」。
しかし一口に「塩」と言っても、その質や体への影響は大きく異なります。
スーパーで並んでいる塩の中には、身体に必要なミネラルを豊富に含んだ自然塩もあれば、ほぼ塩化ナトリウム(NaCl)だけの精製塩もあります。
味の深み、身体へのなじみ方、健康への影響。これらは「どう作られているか」によって決まると言っても過言ではありません。
塩の精製方法いろいろ
塩の作り方には実はたくさんの方法があります。
-
イオン交換膜製法:海水から塩化ナトリウムだけを電気的に取り出す。ほぼ純粋なNaCl。
-
立釜製法:高温・高圧で一気に結晶化。効率的だがミネラルは少なめ。
-
乾燥法:加熱乾燥させて塩を作る。これもミネラルは少なくサラサラ。
-
溶解法:岩塩や塩田でできた塩を水に溶かし、再結晶化。精製度が高くなる。
-
平釜製法:海水を釜でじっくり煮詰めて作る。ミネラル豊富で旨味も感じやすい。
-
天日塩:太陽と風で自然に乾燥させて結晶化。最も自然に近い製法。
このように一言で「塩」といっても、作られ方の違いによって性質がまったく変わります。
今回は触りとして…
まず大きく分けると、「自然寄りの塩」か「精製寄りの塩」か、ここが大きな違いになります。
自然寄りの塩ほど、ミネラルが多く身体にやさしい。
精製寄りの塩ほど、扱いやすいけれど体への負担や偏りも大きい。
ただ、実際に見分けるには「製法」や「成分表示」を理解していくことが大切です。
次回予告
次回は、精製方法の違いから「自然寄り」か「精製塩寄り」かを見極める方法について、詳しくお伝えいたします。
塩は毎日の食卓に欠かせないものです。だからこそ「どの塩を選ぶか」は健康に直結します。ぜひ次回も楽しみにしていただければと思います。