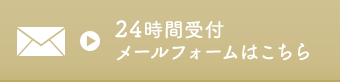こんにちは、浜田山のなんば鍼灸院の南波です。
今日は、患者さんからとても多く寄せられるご質問についてお伝えします。
💬よくある誤解:「保険の部分(1回数百円分)しか使えないんですよね?」
患者さんの多くが、
「医療費控除って、保険診療の自己負担分しか使えないんですよね?」
とおっしゃいます。
実はこれは誤解です。
鍼灸院での自費治療費も、治療目的であれば全額医療費控除の対象になります。
📩きっかけは、ある患者さんからのご質問
ある患者さんから、「保険診療でない自費分も控除できるのか?」という非常に丁寧なご質問をいただきました。
厚生労働省の定義を見ても確かに曖昧な部分があり、私自身も改めて確認する良い機会だと感じました。
もともと「自費分も医療費控除に含まれる」ことは認識していたのですが、
なんば鍼灸院整骨院を開業した約10年前の情報をもとにした知識だったため、
このたびアップデートの意味も兼ねて、国税局に直接確認しました。
☎️【国税局への確認結果】
(国税局電話相談センター:佐々木さん、市川さん)
| 質問内容 | 回答 | 補足 |
|---|---|---|
| 鍼灸院・整骨院の自費治療費 | ✅ 全額対象 | 保険診療でなくてもOK |
| 治療目的で購入したコルセット・漢方薬 | ✅ 対象 | 治療目的が明確ならOK |
| サプリメント | ❌ 対象外 | 医薬品ではないため |
| お灸・置き鍼(薬局購入) | ❌ 対象外 | 治療行為ではないため |
| ワークショップや健康教室 | △ ケースバイケース | 治療目的なら可、養生目的は不可 |
| 病院・歯科での自費診療 | ✅ 対象 | 治療目的であれば全額対象、美容・審美目的は除外 |
| カウンセリング(心療内科など) | ✅ 対象 | 医師の指示・治療計画の一環であれば対象 |
🏥 病院・歯科・鍼灸院すべて合算してOK!
たとえば、
-
鍼灸院での施術費
-
病院での診療費・検査費
-
歯科治療の自費分(セラミックや矯正も「治療目的」なら対象)
-
心療内科のカウンセリング費用(医師指示のもとであれば対象)
これらをすべて合算して1年間の医療費として申請できます。
意外と「鍼灸院は別」と思っている方が多いですが、実際には同じ「治療目的の医療行為」として扱われます。
家族全員分をまとめて申請できるため、10万円を超えるご家庭も少なくありません。
💊 薬局で購入した薬も控除対象に!
「病院の処方箋で買った薬は対象だけど、市販薬はダメ」と思っていませんか?
実はここも見落としがちなポイントです。
国税局の回答では、
症状がある場合に、その症状を緩和する目的で購入した第1〜3類医薬品は全て医療費控除の対象になります。
つまり、風邪薬・胃薬・頭痛薬・湿布なども、
治療目的であればドラッグストアで自費購入した分も含めてOKです。
また、
病院や鍼灸院の指示で購入したコルセットや漢方薬も治療費として控除対象。
「先生にすすめられたから買った」も、十分な理由になります。
💴 医療費控除の計算式
医療費控除額の計算は次の通りです。
(年間医療費の合計 − 10万円)× 所得税率
たとえば年間で30万円かかった場合、10万円を引いた残りの20万円が控除対象。
あとは所得税率を掛け算します。
📊 所得税率と年収の目安表
| 年収の目安 | 所得税率 | 控除の還付額(医療費30万円の場合) |
|---|---|---|
| 約400万円 | 20% | 約4万円 |
| 約600万円 | 20% | 約4万円 |
| 約800万円 | 23% | 約4万6千円 |
| 約1,000万円 | 33% | 約6万6千円 |
| 約1,500万円 | 40% | 約8万円 |
たとえば、年収800万円の方の場合、
(30万円 − 10万円)× 23% = 約4万6千円の還付
そして、この「10万円」という基準は家族全員分の合計です。
ご夫婦・お子様の通院・薬代などを合算すれば、
多くのご家庭が自然に10万円を超えます。
📎 公式情報リンク
✅ まとめ
-
鍼灸院の自費治療費も医療費控除の対象
-
病院・歯科・薬局での治療費も合算して申請できる
-
医師・施術者の指示のもとであれば、薬局購入も対象
-
所得税率によって還付額が変わる
-
家族全員分を合算すれば10万円を超えるケースが多い
✍️さいごに
今回の確認を通して、改めて制度の理解が深まりました。
「知らなかった」で損をする方を少しでも減らせるように、
今後も正確で分かりやすい情報を発信してまいります。